since 16 January 2009
2011�N8���̓��L
| ���ς� |
| �W���Q�W���i���j |
��[����͍������P���Q���ŕۈ牀��ẪL�����v�ɐ�t�E�؍X�Â܂ōs���Ă��܂����B��[����ɂ͈������ǁA��ӂ͋v�X�ɂ��[���Ɠ�l�ŊO�H���܂����B���[���͂��������Ƃƍs�����͂��Ȃ̂ł����A�܂��ߏ��̃X�y�C���������֍s�����ƂɂȂ�܂����B
������̃p�G���A�A�X�y�C�����I�����c�����܂������A���[��A�������������Ȃ��c�B���������������悤�ɂȂ��Ă���A�ʂɐオ�삦���킯�ł͂���܂��A�����ĐH�ׂ����c�Ǝv���ƁA�ȑO�����]�����������Ȃ����悤�ȋC�����܂��B���̂��������邩������܂���B�ʐ^�͎B��܂������A�f�ڂ���قǂ̂��̂ł�����܂���̂Ŋ������܂��B �L�����v�̗l�q�́A�u���O�ɐ����f�ڂ���Ă��܂����̂ŁA�قڃ��A���^�C���ŗl�q�����邱�Ƃ��ł��܂����B�Ȃ��Ȃ��悢�V�X�e���ł���ˁB��[����́A�[���Ɋ�ɓD���������ς���ŋA���Ă��܂����B�R���悶�o������A�݂�ȂŃJ���[���������A�L�����v�t�@�C�A�[��������ƁA�����P�����̊��ɐ��肾������̃v���O�����ŁA��[������y����ł��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����痂����Ȃ��ċA���Ă����悤�ȋC������̂͐e�̗~�ڂł��傤���ˁB���Ȃ݂ɁA���̃L�����v�͂P�O�܂ŎQ���Ȃ̂ŁA��[����]����Η��N���s�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B |
| �Љ�ی��J���m���� |
| �W���Q�W���i���j |
�����͎Љ�ی��J���m�����ł����B���ǁA���͎i�@���m��ڎw�����Ƃɂ��܂����̂ŁA���������Ă��܂��A�^���̂�������ɂ���ẮA�����������獡�����{���ɂȂ��Ă�����������Ȃ�������ł��ˁB
�ИJ�m�ƍs�����m�Ƃ̃_�u�����C�Z���X�i����Ɂ{���Ńt�B�i���V�����E�v�����i�[�����l�����܂��j�œƗ��E�J�Ƃ���l�����\�������܂��̂ŁA��N���ɍs�����m�������������Ԃ������������������Ƃł��傤�B ���̎����́A�T�ˍs�����m����������i���͍��߂ł͂���܂����A�Ƃ͌����Ă����Ȃ�̓�֎����ł��B�����Q�T�Ԃ��炢�����Ă݂����Ƃ�����܂����A���������čs�����m������肫���Ȃ��Ƃ�����ۂ��c���Ă��܂��̂ŁA�����s����������̂�������܂���ˁB �J����@�A�J�����S�q���@�A�J�Еی��@�A�ٗp�ی��@�A���N�ی��@�A�����N���ی��@�A�����N���@�A��ʏ펯�i�J���E�Љ�j�̊e�Ȗڂ������ȖڂƂ��ĉۂ����̂ł����A���̕���̐��ƂɂȂ邽�߂̎��������ɁA�d���̋������悤�Ȗ�肪�����A�܂������ł͂Ȃ��������i�N���z��ی������j�ɂ��Ė�����肪�����o�肳��܂��B���Ȃ݂ɁA���̎����ʼnۂ����m�����āA�������łƂĂ����ɗ��������Ȃ��̂������ł��B |
| �����q�̓��@���މ@ |
| �W���Q�V���i�y�j |
���͎q�ǂ��̍��A�̒�������Ɩڂɂ����悤�ŁA���������ɜ���Ă͂悭��Ȃɒʂ��Ă��܂����B�ҍ����ɐ��a�ɂ��Ďʐ^����̐��������f������Ă��āA�q���S�ɂ��|���a�C���Ȃ����Ďv���Ă��܂����B�K���ɂ��A��[����͍��܂Ő��a�̋^��������悤�ȏǏ�͏o�����Ƃ��Ȃ��̂ŁA���a�Ƃ����a�C���̂̑��݂�Y��Ă��܂����B
���āA�Q�̉����q����T���a�ɜ���Ă��邱�Ƃ��������A�����@�c�B���͔D�P�T�J���ł��̂ŁA�A���̕t���Y���͂������낤�Ǝv���A�w���v��\���o�܂������A���i�͗V�т̗\��D��̎��̗��e���������Ɍ��g�I�ȊŌ�����Ă��ꂽ�悤�ŁA���̏o�Ԃ͂Ȃ��܂܁A�����Ɉ�T�Ԃőމ@���܂����B�ŏ��ɍs���������Ȉ�̔��f���I�m�������悤�ŁA���Ȃ葁���^�C�~���O�ŕa�C���m�m�ł������Ƃ��悩�����悤�ł��B�܂�����ɂ��Ă��A�厖�Ɏ���Ȃ��Ė{���ɂ悩�����c�B ����P�J���Ԃ͕ۈ牀�̓o����~�A�l���݂ɘA��o���̂��m�f�ŁA����ň��Âɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��B�ƂĂ������ȉ����q�ɂƂ��Ă͂炢�ł��傤���ǁA�̗͂����ė]���Ă��鉙���q���Ƃł����Ƃ����Ă���������ςł��傤��(^_^;)�B |
| �G�r���O�n�E�X�̖Y�p�Ȑ� |
| �W���Q�V���i�y�j |
�u�G�r���O�n�E�X�̖Y�p�Ȑ��v�Ƃ����̂��������ł��傤���B����͎��i�����Ȃǂ̕����Ă���l�ɂ͔�r�I�L���Ȃ�ł����c
�E20����ɂ́A42%��Y�p���A58%���o���Ă����B �E1���Ԍ�ɂ́A56%��Y�p���A44%���o���Ă����B �E1����ɂ́A74%��Y�p���A26%���o���Ă����B �E1�T�Ԍ�ɂ́A77%��Y�p���A23%���o���Ă����B �E1������A�ɂ�79%��Y�p���A21%���o���Ă����B �O���t�ɂ���Ƃ���Ȋ����ł��i�l�b�g��ɂ��������̂�q���܂����j�B 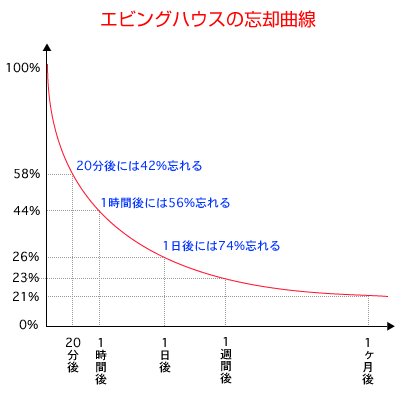 ������l����ƁA�P�J����ɊԈႦ����������Ə��߂Č���悤�Ȉ�ۂ���͎̂��ɓ��R�̂��Ƃł��ˁB ���͎����̋L���͂ɑ���ߐM�����S�Ɏ̂ċ���������ł��܂������A�܂��Â������悤�ł��c�B�ԈႦ�����͂��̓��Ⴕ���͗����ɂ͕��K����Ƃ����p�����K�v�Ƃ������Ƃł��ˁi�Ƃ͌����A���ۖ��Ƃ��ĂȂ��Ȃ������܂Ŏ肪���Ȃ��̂�����ł͂���܂����c�j�B�܂�A�P���֖̊��˔j���Ă����A���Ȃ�̊m���ł��̋L���͒蒅����Ƃ������Ƃł��B�l�ԖY���̂����ʂ̂��ƂȂƎv���A�����͐��_�I�Ɋy�ɂȂ�Ƃ������̂ł�(^_^;)�B�ނ��낻���v��Ȃ��ƁA�ƂĂ�����Ȃ����ǂ��̎������͂���Ă��܂���B |
| �u���T |
| �W���Q�S���i���j |
�u�u���T�v�Ƃ����̂́A�u���b�N�i�[�̌����ȑ�T�Ԃ̂��Ƃł��B������̃T�C�g�ł��Љ�����c�F�������y�Ղł����t���ꂽ�Ȃł��B���̋Ȃ͎��ɂƂ��Ă͏����h�^���I�ȁh�ȂȂ�ł��B
��w�̃I�P�ɓ������ď�����ƂȂ�̂����̔N�̓~�̏��߂ɍÂ�������t��Łi���̃I�P�f�r���[�̓x�[�g�[���F���́u�R���I�����v���Ȃ�2nd�t�ҁj�A���̎��̃��C���Ȃ��u���T�ł����B���͘^���W�ł����̂ŁA�悭���K���i�����Ă��܂������A���̎��́u�Ȃ�ł���Ȃ܂�Ȃ��Ȃ�I�낤�v���Ďv���Ă��܂����B���̓����͂܂��u���b�N�i�[�̗ǂ����S�R������Ȃ�������ł��ˁB���̂������낢��ȍ�ȉƂ̋Ȃ������Ƀu���b�N�i�[���D���ɂȂ�A�@����������肽���Ǝv���Ă��܂������A���̑�̓g�����{�[���t�҂����Ȃ��āA�K�R�I�ɔ�r�I�Ґ��̏������Ȃ���邱�ƂɂȂ�A�����I�P�̊Ԃ̓u���b�N�i�[�����t����@��Ɍb�܂�܂���ł����B���ꂩ��P�O�N�]��̍Ό����o�āA�Q�O�O�R�N�̏H�̂n�a�I�P�̒�����t��Ńu���T�̎�ȑt�҂���邱�ƂɂȂ�܂����B���̋Ȃ̃t�B�i�[���̍Ō�̉��ł���a��i�σ��j�̉����I�P�ōŌ�ɑt�ł����ł��B���̃I�P�l���̓u���T�Ɏn�܂�u���T�ɏI���܂����B�������A�ǂ�����u��R�O�������t��v�ł����B ���̋Ȃ͍ŏ�����ǂ���������悤�ȋȂł͂Ȃ���������܂��i�������t���Ԃ��W�O��������܂�����c�j�A�ǂ���������Ɣ��Ƀn�}��܂���I���߂Ί��ނقǖ����o����Ă�����ł��B���ɍŏI�y�͂̃R�[�_�i�T�U�R���ߖځj����̃��X�g�R���͈����ł��B�����������܂���i�����������Ă����I�P�ɂ́A�u���T�����łR�O��ނ��炢�̂b�c�����L���Ă��āA�t�B�i�[���̃R�[�_��������ׂ�����Ȃ�Ă����u���T�������܂���(^_^;)�j�B |
| �^��̂��X�X�� |
| �W���Q�P���i���j |
�a�r�ňȉ��̔ԑg����f�\��ł��B������T�ԑO�Ȃ̂ŁA���낻��c�u�c�̃f�W�^���ԑg�\�ɂ��o�Ă��鍠���Ǝv���Ĉꉞ�̂��m�点�ł��B�䂪�Ƃ͑����^��\�܂����B
���ɍ��͂��܂蒮���C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��Ă��A����͘^���Ă����đ��͂��܂���B���̐��E���w�̉��y�Ղł��郋�c�F�������y�Ղ���ӂłQ���f���Ă����̂���͂���܂���B���X�X���ł��I 8��27���i�y�j�@�a�r�v���~�A�� �ߌ�11��30���`�ߑO3��30�� ���������c�F�������y��2011����N���E�f�B�I�E�A�o�h�w�� ���c�F�������y�Պnj��y�c���t�� �������ȑ�35�� �j����K.385�u�n�t�i�[�v�i���[�c�@���g�j �������� ��5�� �σ������i�u���b�N�i�[�j ���nj��y�����c�F�������y�Պnj��y�c ���w �����N���E�f�B�I�E�A�o�h ���^�F2011�N8��18�A19�A20�� ���c�F�c��������c�Z���^�[�R���T�[�g�z�[���i�X�C�X�j �����c�F�������y��2009����@�N���E�f�B�I�E�A�o�h�w�� ���c�F�������y�Պnj��y�c���t�� ���u�Ō�̎��̉́v����i�}�[���[�j �������ȁ@��4�ԁ@�g�����i�}�[���[�j �}�O�_���[�i�E�R�W�F�i�[�i�\�v���m�j ���nj��y�����c�F�������y�Պnj��y�c ���w �����N���E�f�B�I�E�A�o�h ���^�F2009�N8��21���A22�� ���c�F�c��������c�Z���^�[ �R���T�[�g�z�[���i�X�C�X�j |
| �čՂ� |
| �W���Q�O���i�y�j |
�����͂�[����̕ۈ牀�̉čՂ�ł����B��N�A�N�������ł��X�y�V�����ȏo����������܂��B�W���ɓ����Ă�����K�̗l�q��搶���畷������Ă��āA��[������悭�撣���Ă���Ƃ������Ƃł����B����͂�[�������Ɍ��ɗ��Ă˂ƌ����Ă����̂Ŏ��M����������ł��傤�B�������[�������N�͓��Ɋy���݂ɂ��Ă��܂����B
�������ׁX�Ƃ����C�x���g����������A�N�������ł��u�悳�����\�[�����߁v���n�܂�܂����B�čՂ�̃��C���C�x���g�ł��B�������ɔN������Ƃ��Ȃ�ƁA���т��тƂ��������ŃO�_�O�_�����Ȃ��A�Ȃ��Ȃ��i�D�ǂ������ł��B��[������Ƃꂸ�ɂ�������Ƃł��܂����B��N�̉čՂ�͂��_�`��S���̂��狃���Ă��Ă��Ȃ��������Ƃ��l����Ɗi�i�̐����ł��I���N�̔N������̏o�����͗�N��������オ���������ł��B�I��������l��l�Љ�Ă�����Ă��鎞�Ɂu�q���[�q���[�v�Ƃ����������ł��܂����B    �I����ɐ搶���畷�����b�ł́A��[����͍���܂ňꂩ���U�t���Ԉ���Ă��đ��̎q�Ɣ��Ό����ɂȂ��Ă��܂��Ƃ��낪�������炵���̂ł����A�{�Ԃ͂����ƏC������Ċ����ɂł��������ł��B �����̂�[����́A�ߑO���̓��}�n�Ŕ��\�A�ߌ�͉čՂ�Ƒ劈��̈���ł����B�����l�I |
| �X�}�[�g�t�H�� |
| �W���P�T���i���j |
�������ɃX�}�[�g�t�H���ɔ����ւ��܂����B���܂ł�Foma�g�т͊ۂR�N�g���܂����B���̌g�я��L���\���N�̒��ōŒ��ł��B
 �w�������@���Galaxy S�ł��B�����ւ��̕K�v�ɔ����Ă����킯�ł͂���܂��A�ŋ�Galaxy S�U���o�Ă���A�^�����@��ł���Galaxy S�͒l���ꂪ�n�܂��Ă��āA�܂��҂ĂΒl�����肵����������܂��A���낻��X����������n�߂Ă����̂ŁA�������������ȂƎv���Ĕ����ւ��Ă��܂��܂����B�|�C���g���R���~�㕪����܂����̂ŁA�����o���͂P���~���ōς݂܂����i���X�T�|�[�g��������j�B ����́A�v�X�ɕ��ȊO�̂��̂Ŏ����̂��߂̔����������܂����B�����Q�N�A�����ƌv������āA���Ȃ获�O��R�₵�Čo��ߌ��ɓw�߂Ă��܂����B�����Ŏn�߂����Ƃł͂���܂����A�ߖ�����ł��Ȃ�����A����͂���łȂ��Ȃ�����ǂ����̂ł��B�t�@�~���X�ɍs���A�w�����̘A���ł���W�����W�����������Ă���̂�ׂŎw�����킦�ĉ䖝���A�A�E�g���b�g�ɍs���Ή��������Ȃ��c�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������ȂǁA���炩�ɗ~���ɋt�炤���Ƃ����Ă���X�g�C�b�N�����ɂ����Ă��Ă��܂����B�������ߖ�Ǝv���ł��傤���ǁA�����Ԃɋy�Ԃƃ{�f�B�[�u���[�̂悤�ɂ��킶��ƌ����Ă�����̂Ȃ�ł��ˁB������A����͎������X�g�C�b�N�ȂƂ��납�班������������Ă��Ƃ����Ӗ�����������܂����B ���͂��傤�ǂ��~�x�݁B�{���A���ɂ͂��~�x�݂͂���܂��A���T�͏��������V�����u��������v�ŗV�ڂ��Ǝv���܂��B �i�NjL�j �̂̌g�т������@�\�E���@�\�ɂȂ��Ă���ɂ�������炸�A�X�}�[�g�t�H���̃g���Z�c�͔����ł��ˁc�B�����炭�l�ɂ���ėp�r������ɂ킽��߂��āA�R���p�N�g�ȃ}�j���A���ł͑Ή�������Ȃ�����Ȃ�ł��傤�ˁB����Ȃ��Ƃ������āA�ݒ蓙�ɂ͂Ȃ��Ȃ���J�������܂����B����Foma�̃��[�����X�}�[�g�t�H���̃��[���ƃt�@�C���`�����Ⴄ�̂ŁA�ϊ��\�t�g���l�b�g�ォ��_�E�����[�h���Ăo�b�ɃC���X�g�[���������ƁA��U�r�c�J�[�h��Foma���[���t�@�C�����R�s�[���āA�o�b�ɂ������U�ڂ��ĕϊ����āA���̌�X�}�[�g�t�H���ɕϊ���̃t�@�C�������[���{�b�N�X�ɃC���|�[�g����Ƃ�����Ƃ��ł���J�������܂���(^_^;)�B�ŋ߁A�N�z�̕��Ƃ����X�}�[�g�t�H�����[�U�[�������Ă��܂����A�ǂ����Ă���낤�Ǝv������A�h�R���V���b�v�ɂ́A�X�}�[�g�t�H���ւ̐�ւ��̂����ɂ��ĕ����ɗ��Ă���l�ł��ӂ�Ă��܂����B�������Ɍg�т̔̔��X�܂ł͒��J�ɋ����Ă���܂���ˁB�i���̓l�b�g���[�N�̃p�X���[�h��Y��Ă��܂��A���s���낵�Ă��邤���Ƀp�X���[�h�������������Ă��܂��A�h�R���V���b�v�ōĔ��s���Ă�����Ă��܂����c�j�B |
| �v���������I |
| �W���P�Q���i���j |
�ŋߎv�������Ȃ����Ƃ��������肷��N���Ȃ̂ŁA�ǂ��ł��������Ƃł����A�v�����������Ƃ͏����Ă������Ɓc�B
���N�̂T���P�U���̕x�m�܌ւ̃h���C�u�̓��L�̒��ŁA��������w�P�E�Q�N���̎��ɃI�P�ʼn��̌W������Ă����̂��v�������Ȃ��Ƃ����b�������܂������A�{�[���Ƃ��Ă��鎞�ɋ}�Ɏv���o���܂����B���́u�^���W�v������Ă��܂����i���[���́u���h�W�v�j�B �����̃I�P�ł͍��t�̗��K�����ׂĘ^�����Ă��܂����B��w�ɂ͗��h�ȍu���������āA�����ɂ͂����Ƃ����O�_�݂�}�C�N���t���Ă��āA�X�^�W�I���Ȃ���̂��Ȃ���I�ȋ@�킪�������^��������������ł��ˁB�^���W�́A���K���ԑO�ɘ^���ł����ԂɃX�^���o�C�����Ă����A�w���_�������Ɠ�����REC�{�^���������āA�X�O���e�[�v����K���Ԓ��Ɉ�x�������āi�I�[�g���o�[�X�@�\���g�����t���K���R���Ԃł����̂łP��e�[�v��������悢�j�A���K��Ɍ���i���ЂÂ��j����A�Ƃ������d���ł��B���\�ʓ|�Ȏd���������̂ɉ��ō��܂ŖY��Ă����낤�c�B �W�̎d�����A����Ԃ������NJy��̉����������̌W�����蓖�Ă���̂��ʗ�ł����B�t�����`�z�����Ȃǂ̂P�Ȃ�����ɐl����K�v�Ƃ���y��������ẮA��{�I�ɊNJy��̂P�N���͌����Ȃɂ͂̂��Ă��炦�܂���B�����ė��K�͎d�グ��̂���ςȌ����Ȃ̗��K�����S�ƂȂ�܂��̂ŁA�K�R�I�ɂ���Ԃ������Ȃ�܂��B �^���Ȃ��Ē����̂��Ǝv���ł��傤���ǁA�܂��݂�Ȃ悭�^�������e�[�v���Ă��܂����ˁB������A�^�����ł��Ă��Ȃ��Ȃ�Ă������Ƃ����������ɂ͐�y����ڂ̐F��ς��ē{��ꂽ���̂ł��B�Ȃɂ��X�^�W�I�̂悤�Ȗ{�i�I�ȋ@�B�Ȃ̂ŁA������Ƒ�����ԈႦ��Ƙ^���ł��Ă��Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͏\���ɂ��蓾����ł���B���K��ɕ����ŁA���������̉��t���Ȃ���A������A�ǂ̂悤�ɉ��t���ׂ�����^���ɋc�_������c�Ƃ݂�ȉ��y��{���Ɉ����Ă��܂����ˁB��[�A���̍��͂悩�����c�B�ǂ�������������ԂɂȂ��ƓڂɃm�X�^���W�[�ɐZ���Ă��܂��č��������̂ł��ˁc�B |
| slow in, fast out |
| �W���P�O���i���j |
���T���炨�~�x�݂̐l����������ł��傤���˂��B�����͉^�]������Ă���Ȃ��Ƃ����Ԃ����|�I�ɑ����ł����A���T�ɂȂ��ċ}�Ɂu�T���f�[�E�h���C�o�[�v���������悤�Ȋ��������܂��B���ɒʍs������Ă�����A�H�n����o�ė��鎞�ɍs���̂��s���Ȃ��̂��͂����肵�Ȃ��Ԃ������ł����A�n���h��������u���[�L���O���u���v�H�v���Č��������Ȃ�悤�ȎԂ������ł��B���炢���͔̂����Ȃ���c�B
���K���͖Ƌ����擾���Ă�����ɗ��Z�p�͂قƂ�Nj����Ă���܂��A�u�X���[�C���E�t�@�[�X�g�A�E�g���s�v�����͗��ɓK���Ă��āA���s��A�K�v�Ȃ��Ƃł��ˁB�J�[�u���Ȃ���Ƃ��Ɂi�Ȃ���O�ł͂Ȃ��j�u���[�L���₽�瓥��ł�����A�J�[�u�̌㔼�ŃA�N�Z���܂Ȃ�������c�Ƃ܂����𑖂��Ă���Ǝ��ɂ��������Ԃ͟T�������킯�ł��B�������ڂ̑O�𑖂��Ă���Ԃ�����Ȋ����ŁA����̉ʂĂ̓n���h�����߂��ĉE�܌�ɑΌ��Ԃɐڋ߂��čs���n���B������ƖƋ��Ԃ�������������Ȃ��̂��I |
| Keeping a Diary |
| �W���R���i���j |
�����͓��L������K���ɂ��āc�B�����ŋ߁A�g�߂œ��L�������n�߂��Ȃ�Ă����b�������ɂ͂��肵����ł����A���낻��ŏ��́h�֖�h�ɍ����|���鍠��������܂���̂ŁA�����̈Ӗ������߂āc�B
�u����������L���������Ƃɂ��悤�v�Ƃ����ĎO���V��ŏI����Ă��܂����Ƃ����o���͒N�������邩�Ǝv���܂��B�������܂ʼn�������܂��Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�Q�O�O�S�N���U����t���n�߂��A�i���O���L�͂P�������������ƂȂ��V�N�W�J���ڂɓ���܂����B���̍���͑����Ă���̂��H���肫����Ȃ��Ƃ��������܂��A�������Љ�����Ǝv���܂��B�������L�����������ȂƎv���Ă�����ɂ͑����Ȃ�Ƃ��Q�l�ɂȂ邩������܂���B �����L���������Ԃ͂T���܂ŁI �u��[���A����������L�������I�v�ƈӋC���ނƏ����͋C��������܂���ł��Ȃ蕪�ʂ�������ł��ˁB����Ⴀ�����ł��A�������Ǝv�������̓��ł����珑���܂���B�ł������ɂȂ�Ə����̔����A���X���ɂ͂���ɔ����ɁA�R����ɂ͂����ʓ|�ɂȂ��ď����̂���߂Ă��܂��c�Ƃ��������ő����Ȃ��Ȃ��Ă��܂���ł��ˁB���L���������Ԃ��m�ۂ��Ȃ��Ɓc�Ȃ�Ă����C�����ɂȂ��Ă��܂��Ă�����A��������̓��^�C�����O�̏�Ԃł��B�ł��T�����x��������ǂ�ȑ��Z�Ȑl�ł��P�o�ł��Ȃ��l�Ȃ�Ă��Ȃ��͂��ł��B�܂��T�����x�̂��Ƃ�������A�����ꂻ�̓��ɏ����Y��Ă��A�����ɖ��ߍ��킹���ł��܂��i�A���Q���ȏ㗭�߂�̂͂m�f�j�B ����w�m�[�g�͎g���Ă͂����Ȃ��I ��̘b�Ɗ֘A���Ă��܂����A���X�̏������ʂ͂�����x���ł��邱�Ƃ��]�܂����ł��B��w�m�[�g�œ��L�������ƁA���q�ǂ����͂P�y�[�W�����Ă��܂��܂����A����Ŗ������Ă��܂��ė����͂��������C�ɂȂ�Ȃ����̂Ȃ�ł��ˁB������w�m�[�g���g���Ȃ�A�����ŏ�����ʁc�܂��T�s���炢�ł��傤���A�T�s���Ƃɐ��������ċ���Ă����ׂ��ł��傤�ˁi�{���͎����g���Ă��锎�i�ِV�Ђ̂T�N�A�p���L�����X�X���������Ƃ���ł��j�B�����āA�ǂ����Ă������������Ƃ�����������͕ʓr����������ł��i���̏ꍇ�́A��[����̒a�����̓��L�����͖��N���Ȃ�̃{�����[���ŏ����Ă��܂����j�B �����e�̃n�[�h�����グ��ȁI �����K�����̓����������ƂȂǂ���͏����Ȃ��Ắc�Ǝv���Ă���l�������Ǝv���܂��B���ꂪ�ł������Ȃ��Ȃ�v�����ƌ����܂��B�ɒ[�Șb�A���̓��̏o�����̗���ł������Ǝv���܂��B�������ď����ł��i���������͂��������Ȃ�Ďv���Ƃ��̂����ʓ|�ɂȂ��Ă���̂��ڂɌ����Ă��܂��B�����������Ƃ͌��J�^�̃u���O��z�[���y�[�W�̓��L�Ƃ��Ŋ撣�������ł��B �ȏ�̂��Ƃ܂��āA�u�������炢�͏����Ȃ��Ă�������v�Ƃ����C�������̂ĂāA�K��������邱�Ƃł��B���̂����A���L�������Ȃ��Ǝ����Y�ꂽ�悤�ȋC�����������o����悤�ɂȂ�A��炸�ɂ͂����Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B �ƁA�G�������Ȃ��Ƃ������Ă��܂����A�����g�A���L���t���邱�Ǝ��̂ɂ܂��傫�ȈӖ��͌��������Ă��܂���(^_^;)�B�ł��u�p���͗͂Ȃ�v�ƌ����܂��̂ŁA��������̖��ɗ����ȂƔ��R�Ƃ͎v���Ă��܂��B |