since 16 January 2009
2013�N2���̓��L
�O�̑����ł��B�C���ȘA����f���邽�߂����ɏ����Ă���l�܂�Ȃ��l�^�ł��݂܂���m(__)m�B���̋C���]���ɏ��������M���Ă�����A��ɂ���Ē����Ȃ��Ă��܂��܂����c�B�����������珑���Ă��邾���ł�����A�ǂ����X���[���ĉ������B
�s���Y�o�L�@�̏������ł́A�����ł������u�g�O���v�Ƃ����̂�����܂��B
�o�L�\���ɂ́A�\������ɂ������ĉ����ŏ��ɐ\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̐\�����̃��[��������܂��i�Ⴆ�A�����̑㗝�ł�����o�L�\���ŁA���������ɂ������āA���L���̖��`���c���̂܂܂������̂ŁA��ɑ����o�L�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����͓̂T�^��̈�ł��j�B��������背�x���ȏ�̎��͂����������[���͓��R�������Ă��܂��B �Ƃ��낪�A�c��ȏ���c�����Ȃ���ǂ�ł���ƁA�ŏ��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��o�L�\���ɋC�Â��Ȃ��Ƃ��A�Q�̐\�����ꊇ�\���ł���̂ɋC�Â��Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��N���肦�܂��i��̗�قǕ�����₷�������Ă���킯�ł͂Ȃ��ꍇ���قƂ�ǂł��j�B ���ėp���͂���Ȋ����̂��̂������ł��i����~�X���������̗p���ł͂���܂���j�B 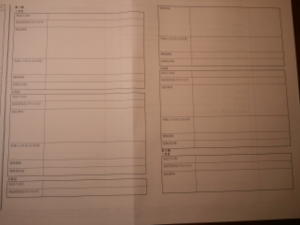 �u�P���ځv�A�u�Q���ځv�A�u�R���ځv�A�u�S���ځv�Ƃ����悤�ɘg������Ă��܂����A�\�������͑S���łS���ƌ��܂��Ă���킯�ł͂���܂���B�R����������܂��A�T����������܂���B�����āA������L�̂悤�ȊԈႢ���������Ƃǂ��Ȃ邩�c �i�ꊇ�\���ɋC�Â��Ȃ������ꍇ�j �y���̓��āz �P���ځF�u�`�v�A�Q���ځF�u�a�v�A�R���ځF�u�b�v�A�S���ځF�u�c�v �y�͔͉z �P���ځF�u�`�v�A�Q���ځF�u�a�b�v�A�R���ځF�u�c�v�A�S���ځF�u�\���s�v�v �ǂ��������Ƃ�������܂����H�����炵�����菑�����Ƃ��Ă��A�Q���ڈȍ~�͓_�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��ł��B�������A�{�����ł���Ă��܂��ƁA���ɑ���ʼnX�������т�����Ă��Ă��A�����̑���ŕs���i�ƂȂ�܂��B���N��萔�̍��i�����҂�����ŗ܂�����ł��܂��B������ނ��Ⴂ�܂����A�����������i�͏��Ɠo�L�@�ɂ����N�d�|�����Ă��܂��B ����̓����Ŏ�������Ă��܂����~�X�͏�L�́u�i�ꊇ�\���ɋC�t���Ȃ������ꍇ�j�v�A�܂��ɂ��̂��̂ł��c�B����̓��i���Q�����d�|�����Ă��āA�P�ځi�P���ځj�͖����������܂������A�Q�ڂłЂ��������Ă��܂��āc�B ����͂��܂��܁A���̂R�����̐\���Ƃ͕ʂɂQ�����̐\���̖�肪�o�Ă��āA������ł���Ȃ�Ɏ��܂����̂ŁA�S�̂Ƃ��ẮA�قƂ�Ǔ_�����Ȃ��Ƃ����悤�ȑ厖�̂ɂ͂Ȃ�܂���ł������A���̍\���ɂ���Ă͕����_���S�����Ȃ��Ƃ������ԂɂȂ肩�˂Ȃ������~�X�ł��B �ߋ��R��̓����͉��Ƃ��u�g�O���v�����͉�����Ă������ǂȂ��c�B��N�̖͎��̎��Ȃǂ͂R�̃��i�ɂR�Ƃ������������Ă��܂����Ƃ������Ƃ�����܂���(^_^;)�B������l����Ə����͐������Ă���̂�������܂��ǂˁc�B�܂��{�����܂łɓ����E�͎��ŏ������������@��͏��Ȃ��Ƃ����ƂP�T��܂����A����g�O�������邱�Ƃ��c�B �����������Ƃ͎N�����d�˂�قǕ|���������Ă����Ȃ����Ƃ����C�����܂��ˁc(+o+)�B �܂����͎��ł�����u���i�v�Ƃ������Ă܂����A�����������Ƃ������ł���Ă��܂��ƁA�\���͋p������Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��̂ŁA�����Ō����������͓̂��R�Ƃ����Γ��R�Ȃ�ł��B ����ł��̃l�^�͂����܂��ł��B |
�ߑO�O�����߂��Ă��炢���Ȃ��d�c�B���͂��̎����傤�ǃt�@�~���X�ŕ����ŁA�}�ɐ^���ÁB�t�@�~���X�̃u���[�J�[���������̂��Ǝv���܂������A����ɕ�������l�q�͂���܂���B�O������ƐM���@���_���Ă��܂���̂ŁA��т���d�������Ƃ�m��܂����B
�M�����_���Ă��Ȃ��̂ɁA�Ԃ��т��т���Ă��܂������ǁA�悭����Ŏ��̂ɂȂ�Ȃ������Ǝv���܂��ˁB����ȏ�Ԃł�����A�ԂŋA�邱�Ƃ��ł��܂��A�ӂ�͎����̈łł�����A�����ċA��̂��댯�ł��B��������܂œ����܂���B�X�������E�\�N���e�[�u���Ɏ����Ă��Ă���܂����B �����Q�����Ȃ��Ǝv���Ă���Ƃ���ɁA���[���d�b�A�������d���̖͗l�B��[����͈�U�Q����N���Ȃ��z�ł�����A�����ƒ�d�̂��ƂȂ�ċC�t���Ă��Ȃ��ł��傤�B �X�}�z�œ��d�̃T�C�g������ƁA���c�s�Ɖ��l�s�t��E��̈ꕔ����d���B���Ȃ�s���|�C���g�ł��B����̕ϓd���Ɉُo�Ă����ł��傤�B ���ǂR�O�����炢��d���Ă��܂����B����ɂ��Ă������������̓�����Ȃ��Ă悩�����ł���B���̂R�O���ł��G�A�R������Ă��Ȃ�X���̎������������Ă��܂��������(+o+)�B |
���i���ē��X���i���Ă��鎎���̂��Ƃɂ��ď��������܂��B���݂܂��A�������ɂ͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����̂ŁA�Q��ɕ����ď������Ē����܂��B�@���̂��Ƃɂ��ď����킯�ł͂���܂���B�����A���e�I�ɂ��܂���������Ă����傤���Ȃ��Ǝv���܂����A���X�Ƃ���Ȃ��Ƃ�����Ă�����悤�Ȃ��g���ł͂���܂���̂ŁA�Ȍ���������₷�������悤�ɓw�߂܂����A���������Ȃ����̓X���[���Ă�������m(__)m�B �i�@���m�����́A���_���Q�W�O�_�ŁA�ߑO����i�R�T��E�P�O�T�_�j�A�ߌ����i�R�T��E�P�O�T�_�j�A�����i�s���Y�o�L�@�R�T�_�A���Ɠo�L�@�R�T�_�j�ō\������Ă��āA���ꂼ��Ɋ�_�i���胉�C���j���ݒ肳��āA��N�Q�O�O�_����Q�Q�O�_���炢�ō��i���C����������܂��B
�������ɍ��i���Q����̍��Ǝ��i���������āA���i�ł���_���Ɏ����Ă����͍̂�����ɂ߂܂��B���鏊�Ɂh�g���b�v�h��h�n���h���d�|�����Ă��܂��B ����͒��r���[�ɕ������Ă���ƊԈႦ��悤�ɏ�肭����Ă��āA���ɐ��m�Ȓm�������߂��܂��B�����ĈՂ����Ƃ͌����Ȃ������肪���Ԓ��łW�T�����x�Ƃ�Ȃ��Ă͂����܂���̂ŁA�������ő�̓�ƌ����Ă������ł��B�ߑO�E�ߌ㗼���̑���̑�����z������̂́A��N�S�҂̂U�`�V�����x�ƌ����Ă��܂��B����͓��X�Ђ�����ς��E��Œn���ɂ�邵������܂���B �����āA���̍����o�[���z�������Ƃɂ́A���낵���������̃��i���҂��Ă��܂��i�{�����ł́A�������͑���̑�����N���A�����l�̂ݍ̓_����܂��j�B�������Ǝv���Ă���̂͂��̃��i�̘b�ł��B�����̓����ʼn������~�X�����܂����i�ƌ����Ă��A���̎��̎��͂ł͉������鎑�i�͂Ȃ��̂�������܂���j�̂ŁA�����͂���ɂ��ď������Ƃɂ��܂����B ��N�A�s���Y�o�L�@�ɂ����Ɠo�L�@�ɂ��A���m�Ȓm���ƍ������ӗ͂Ə��W��͂��Ȃ��Ƒ匸�_�������邱�ƂɂȂ�h�n���h�����ߍ��܂�Ă��܂��B�e�o�L�@�̏������́A���ꂼ��P�O�`�P�T�y�[�W���x�Ƒ�σ{�����[��������܂��B���@���Ж@���̒m������g���āA�c��ȓ��e��Z���ԂŔc�����āA�������āA�ǂ������o�L�\�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����f�������鎖����`���ł��B���e�c���E����E�ׂ��ׂ��o�L�̌���ɂ������鎞�Ԃ͊e�o�L�@�ł��ꂼ��Q�O�`�R�O�����x�A���Ă������̂ɂ������鎞�Ԃ͊e�o�L�@�ł��ꂼ��Q�O�`�R�O�����x�B����������R�T��ƕ������킹�łR���Ԃ̒��ł�肭�肵�Ȃ���Ȃ�܂���B���i�҂ł��T�O�_�ȏ�^�V�O�_����l�͂����킸���ƌ����Ă��܂��̂ŁA�����Ƀ~�X���ŏ����Ő蔲�����邩�������̕�����ڂƂȂ�܂��B �����̓N�^�N�^�Ȃ̂ŁA���̑����͎���ɂ��܂�(-_-)zzz�B ���Â��� |
�����͐e�o�J�L���ł�m(__)m�B ��[����́u�Ǐ��́v�A�ڊo�܂����i�������Ă��܂��B���w���ɂȂ��Ă��낢��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂������A���̒��ł��A�l�I�ɂ͍ł������]�����Ă���̂��u�Ǐ��́v�ł��B �ċx�݂Ɂu����p���v�̓`�L���x�x�݂��Ȃ��牽�Ƃ��Ǘ��ł����Ƃ����b�͈ȑO���̓��L�ł����������Ƃ�����܂����A���ł͂Q�O�O�y�[�W�゠��`�L�����̋C�ɂȂ�R�`�S�����炢�œǗ����܂��B���������̊Ԃɂ��A���Ȃ�ǂ߂�悤�ɂȂ��Ă���̂ɂ�����������܂��i���ʂɁu�`���āv�Ƃ��ǂ�ł܂�(^.^)�j�B �������N�����̖{�����낢��ǂ�ł��܂����A��[���ǂ�ł���|�v���Ђ̓`�L�͂P�O���炢�̎q��Ώۂɂ��Ă��܂��i�Q�O�`�R�O�N�O�̔ł̖{�Ȃ̂őΏ۔N��͍���������ǂ��Ȃ̂��肩�ł͂���܂��c�j�̂ŁA�ǂނ̂͂��Ȃ��ςȂ͂��ł��B�����炭�A��[����͂����銈���A�����M�[�̂悤�Ȃ��̂͑S���Ȃ���ł��傤�ˁB ���͊������ꂪ���Ȃ�i��ł��܂�����A�ڂ�ڂ₷��ƍ��w�N���炢�̎q�ł����������{�͓ǂ܂Ȃ�����ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂�������܂���ˁB�����v���ƁA���ꂾ�����������Ƃ͌����܂��A��͂�Q�[���Ƀn�}�点�Ă͂����Ȃ��Ɖ��߂Ďv���܂��ˁB �ƂĂ��ǂ��K�����g�ɂ��܂����̂ŁA����Ƃ������Ăق����Ǝv���܂��B��������A���̂悤�Ɏ̍���ŋ�J���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�I����͂͂��ׂĂ̕��̌��ł�����A�{�����͓ǂ�ł����đ��͂Ȃ��ł���ˁI �u����p���v�A�u�x�[�g�[���F���v�A�u���C�g�Z��v�A�u�G�W�\���v�A�u�V���o�C�c�@�[�v�ƂT���ڂɓ���܂����B���́u�t�@�[�u���v�������ƌ����Ă܂��B |




