竹山道雄「ビルマの竪琴」
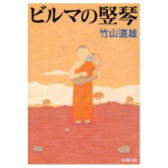
読了日:2009/09/09
個人的評価:★★★★☆
「赤とんぼ」連載 233ページ(新潮文庫・1959/04/15)
| <あらすじ> ビルマの戦線で英軍の捕虜になった日本軍の兵隊たちにもやがて帰る日がきた。が、ただひとり帰らぬ兵士があった。なぜか彼は、ただ無言のうちに思い出の竪琴をとりあげ、戦友たちが合唱している「はにゅうの宿」の伴奏をはげしくかき鳴らすのであった。戦場を流れる兵隊たちの歌声に、国境を越えた人類愛への願いを込めた本書は、戦後の荒廃した人々の心の糧となった。 |
誰もが知る名作を20数年ぶりに手にとってみた。おそらく最後に読んだのは、市川崑監督の同名の映画を映画館へ観に行った直前だろう。映像の印象が強く残っているためか、水島上等兵=中井貴一、隊長=石坂浩二、おばあちゃん=北林谷榮を思い浮かべながら読んでいた。改めて読み返してみると、映画は原作にかなり忠実だったようだ。 本作品は、戦後間もなく、童話雑誌「赤とんぼ」の編集長から独文学者である竹山氏に児童向けの作品を依頼したことがきっかけだったようである(本作品は竹山氏が唯一書いた小説だそうだ)。竹山氏はビルマ戦線に行っていたわけではないばかりでなく、軍隊生活の経験もないことから、必ずしも描かれていることが事実ばかりではないようであるが、本作品を読んだ人にとっては、ミャンマーと言えば「ビルマの竪琴」というくらい強烈なイメージが残っていることだろう。 平易な文章で書かれているため、大変読みやすく、作者のメッセージがストレートに伝わってくる。言うまでもなく、内容はむしろ大人向きのものだ。三部構成になっており、第一部、第二部は戦後ビルマから帰還した一人の元兵士の思い出話、第三部は水島上等兵が隊長・隊員に宛てた手紙となっている。 部隊から1人離れて行方不明となっていた水島上等兵が、日本へ帰る部隊と行動をともにするか悩んだ末、ビルマ僧として異国の地にうち捨てられた無名戦士たちを弔うためにビルマに残ることを選択する。水島の心の葛藤、隊長をはじめとする隊員たちの水島への想い、つらい戦争の中で音楽がどれだけ隊員達の安らぎになっていたかなどが切々と描かれている。ビルマの赤い土、無念の死を遂げた日本兵の死屍累々、黄色の袈裟をまとい肩に色鮮やかな鸚鵡を乗せた水島の姿が目に浮かぶようである。 一度は読んでみるべき作品だ。未読の方は是非とも涼しくなる前に読んでみたら如何か。今度はDVDを借りて映画を改めて観てみようかな。竪琴で奏でられる「埴生の宿」が聴きたくなってきた。あのアルペジオ(分散和音)を思い出すと胸が締めつけられるような切ない気持ちになる。きっと少年時代に刷り込まれたものなのだろう。 |